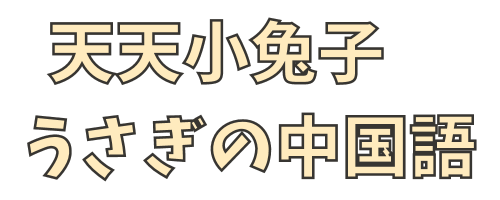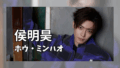中国文学史において、屈原(くつげん/Qu Yuan)は特別な存在です。彼は戦国時代の楚という国に仕え、国家への忠誠と理想を追い求め、最後にはその身を汨羅江(べきらこう)に投じました。その生涯は、ただの詩人にとどまらず、一人の政治家として、また理想家として、壮絶な物語に彩られています。
この記事では、屈原の波乱に満ちた人生を、政治・外交・文学・文化の側面から詳しく紹介します。
高貴な出自と若き才能
屈原は紀元前340年ごろ、楚の国(現在の中国南部)に生まれました。彼は名門貴族の家系に属し、幼いころから学問に励み、詩や政治にも卓越した才能を発揮します。
やがて、楚の懐王(かいおう)に重用され、若くして高官「左徒(さと)」に任命されました。この職は、現代でいえば宰相にあたるような重要な地位で、国内の改革や対外政策を主導しました。
理想主義と腐敗との闘い
屈原は忠誠心が厚く、国を清廉に保つための改革を進めようとしました。しかしその高潔な姿勢は、既得権を持つ貴族や保守派にとっては邪魔な存在でした。
屈原は、秦という強大な国家の脅威に対抗するため、他国(特に斉)との同盟=「合従策(ごうしょうさく)」を唱えていました。しかし、秦との融和を望む派閥の重臣たちから反発を受け、懐王の信任も次第に失っていきます。
やがて、屈原は讒言によって政界から追放されてしまいました。
張儀の策略と懐王の誤判断
屈原の失脚後、秦の恵王は楚と斉の同盟を恐れ、策士張儀(ちょうぎ)を楚に送り込みます。張儀は、楚が斉との同盟を破棄すれば秦は土地を与えると懐王に持ちかけます。
懐王はこの言葉に乗り、斉との同盟を破棄しますが、秦は土地を渡さず、逆に裏切りました。屈原はこの事態を予見し、王に忠告していましたが、再び耳を貸されることはありませんでした。
懐王、秦で客死
この後、懐王は関係修復のために自ら秦を訪れますが、これは罠でした。王は捕らえられ、帰国を許されず、秦で客死します(紀元前299年)。この出来事は、楚にとって政治的にも精神的にも大打撃でした。
頃襄王の即位と屈原の再追放
懐王の死後、王位を継いだのは長子の頃襄王(けいじょうおう)です。しかし、彼の政権も親秦派が主導権を握っており、屈原のような改革派を冷遇しました。
屈原は再び讒言(ざんげん)によって辺境に追放され、政治の表舞台に戻ることは叶いませんでした。(讒言とは他人を陥れるために、ありもしない悪口や中傷を上の立場の人に告げること。)
放浪と詩作の日々
政治の場から退けられた屈原は、失意の中で各地を放浪します。しかしその期間、彼は数々の詩を残し、その多くが『楚辞(そじ)』という詩集に収められました。
特に代表作『離騒(りそう)』は、忠誠、理想、孤独、絶望が融合した長編叙事詩であり、中国文学に新たな表現の世界を開きました。
汨羅江への入水
紀元前278年、秦の名将・白起(はくき)が楚の都・郢(えい)を攻め落としたという報が届きます。祖国の滅亡を目の当たりにした屈原は、すべてを失った絶望の中、湖南省の汨羅江(べきらこう)に身を投じて命を絶ちました。
彼の死は、「忠義を貫いた詩人」として、後世に語り継がれることになります。
屈原の死と端午節の起源
屈原の死を悼んだ人々は、魚に遺体が食べられないようにと粽(ちまき)を川に投げ入れ、太鼓を打ち鳴らして霊を鎮めようとしました。この風習が、やがて端午節(Duānwǔ Jié)として中国全土に広まりました。
現在でも旧暦5月5日には、屈原を偲んで粽を食べたり、龍舟(ドラゴンボート)を漕ぐ競技が行われています。
屈原の意義と遺産
屈原の生涯は、政治家としての理想と失敗、そして文学者としての永遠の名声を併せ持っています。彼の作品は、個人の内面を表現する詩の先駆けとして、中国詩歌の発展に大きな影響を与えました。
また、彼の忠誠と犠牲の精神は、歴代の中国人に「愛国」の象徴として深く刻まれています。
まとめ
屈原は、単なる詩人ではありませんでした。彼は、国を思い、道を説き、しかし時代に見捨てられた悲劇の英雄です。政治の策謀に翻弄されながらも、信念を貫き通した彼の人生は、今もなお語り継がれ、端午節という形で現代に生き続けています。
彼の詩と精神に触れることは、私たちに「信念を持って生きるとはどういうことか」を問いかけてくれるのです。
屈原の作品
「離騒」「九歌」「天問」「九章」「遠遊」「卜居」「漁夫」
「大招」(屈原あるいは景差作)
これらは「楚辞」にまとめられています。