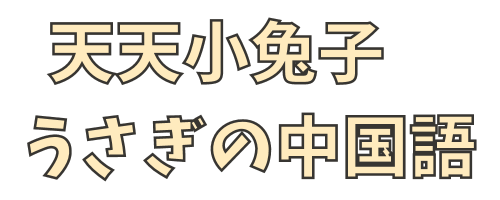中国の伝統的な祝日のひとつ「端午節(たんごせつ/Duānwǔ jié)」は、毎年旧暦の5月5日に行われ、粽(ちまき)を食べたり、ドラゴンボートレースを楽しんだりする日として知られています。
実はこの端午節、起源については複数の説が存在します。本記事では、代表的な三つの説を紹介し、それぞれの意味や文化的背景を解説します。
🐉 1. 屈原追悼説(最も有名な説)
端午節といえば、戦国時代の詩人・屈原(くつげん)を思い浮かべる人も多いかもしれません。屈原は楚の国の高官でしたが、国の腐敗に失望し、旧暦5月5日に汨羅江(Mìluó Jiāng、べきらこう)に身を投じて命を絶ったと伝えられています。
地元の人々は彼を悼み、川に粽を投げたり、太鼓を鳴らして魚から遺体を守ろうとしたという伝説があります。この故事が、今日の粽やドラゴンボート競争の由来となったと言われています。
🌿 2. 厄除け・疫病払い説
古代中国では、旧暦5月は「毒月」とされ、病気や災厄が増える不吉な時期とされていました。そのため、端午節には邪気を払うためのさまざまな風習が生まれました。
たとえば、菖蒲やよもぎを門に飾る、香袋(香囊)を身に付ける、薬草を煎じて飲むといった健康祈願の習慣です。これらの風習は屈原とは無関係に、民間で独自に発展したと考えられています。
🌾 3. 農耕儀礼・祖霊信仰説
端午節は、自然信仰や農耕文化と結びついた季節の節目としての性格も持っています。水難や作物の無事を祈る儀式、舟遊び(龍舟の原型)、供物の文化などがこの説の中核です。
祖霊への感謝や自然への畏敬を込めた伝統行事として、地域によっては現在でもその面影を残しています。
🎏 日本の「こどもの日」との違い
日本でも5月5日は「こどもの日」として親しまれていますが、その由来は中国の端午節とは異なり、日本独自の歴史と文化の中で発展してきました。
▷ 起源は中国の端午節
こどもの日の元となった「端午の節句」は、奈良時代に中国から伝わった五節句の一つです。もともとは季節の変わり目に災いを払う厄除け行事として行われていました。
▷ 武家社会で「男子の節句」に
平安時代には宮中行事として定着し、やがて武士の時代になると、「菖蒲(しょうぶ)」の葉が剣に似ていることや、「尚武(しょうぶ=武を尊ぶ)」という言葉に通じることから、男児の健やかな成長と出世を願う日として意味合いが強まりました。
このころから、鎧兜や武者人形を飾る習慣が生まれ、戦国時代・江戸時代を通して広く一般にも広がっていきます。
▷ 現代の「こどもの日」へ
1948年(昭和23年)、日本政府は5月5日を「こどもの日」として国民の祝日に制定しました。この日には、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」ことが趣旨とされています。
つまり現代のこどもの日は、男女を問わずすべての子どもの成長と幸せを願う日となっています。
▷ 主な風習
こいのぼり:滝をのぼる鯉のように、子どもがたくましく育つことを願って飾られる
兜や武者人形:厄災から守り、勇ましく成長することを祈って飾る
柏餅・ちまき:柏の葉は「家系が絶えない」縁起物。ちまきは中国伝来の風習が残る地域も
菖蒲湯:菖蒲をお風呂に入れて無病息災を願う
📌まとめ
端午節は単なる年中行事ではなく、屈原の精神、民間信仰、そして自然との関わりが重なり合った、非常に奥深い文化行事です。それぞれの起源を知ることで、粽を味わう意味やドラゴンボートの迫力が、より身近に感じられるかもしれません。
一方で、日本のこどもの日は、中国の端午節に由来しながらも、武家社会や戦後の文化背景の中で独自に発展した行事です。同じ5月5日でも両国の文化の違いが見て取れますね。